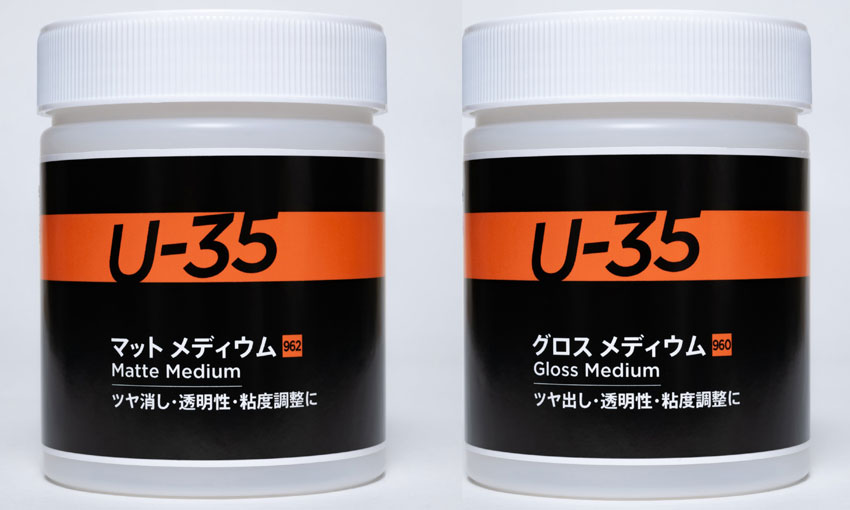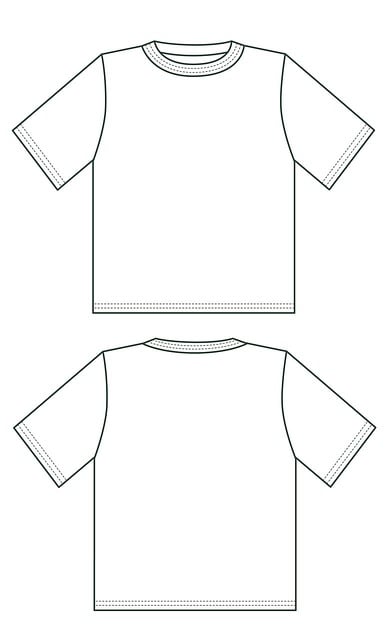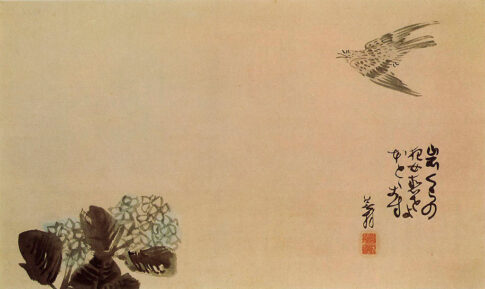はじめに
絵画制作において、絵具の質感や仕上がりをコントロールすることは非常に重要です。特にアクリル絵具では、色そのものだけでなく「表面のツヤ感」や「透明感」を工夫することで、作品の印象が大きく変わります。その際に活躍するのが「マットメディウム」と「グロスメディウム」です。
両者は一見似たような補助材ですが、実際には仕上がりの表情や使う場面に明確な違いがあります。本記事では、両者の特徴と使い分けのコツを解説し、実際の制作現場でどのように活用できるかを紹介します。
マットメディウムとは?
特徴
- 乾燥後に光沢を抑えたマットな質感を与える
- 絵具の発色をやや落ち着かせ、しっとりした雰囲気に仕上げられる
- 塗膜は不透明感が増し、反射を抑えるため落ち着いたトーンの表現に向いている
メリット
- 光の反射が少ないため、写真撮影や展示会場で作品が見やすい
- 絵の具に混ぜると乾燥後の艶を抑えられるので、全体を統一したマット調にできる
- パステル調やソフトな印象を与えたい作品に適している
注意点
- 色がやや沈んで見えるため、鮮やかさを強調したい場面には不向き
- 塗り重ねると粉っぽい仕上がりになる場合がある
グロスメディウムとは?
特徴
- 乾燥後に光沢のあるツヤを与える
- 色の深みや鮮やかさを強調し、透明感を高められる
- 塗膜は滑らかで、反射により高級感や華やかさが出る
メリット
- 鮮やかな発色を活かしたい場合に効果的
- レイヤーを重ねても透明感を損なわず、奥行き感を出せる
- 光沢により視覚的なインパクトを強められる
注意点
- 強い反射が出るため、展示環境によっては鑑賞しづらくなる
- 過剰に使うとテカリすぎて不自然な仕上がりになる
マットとグロスの仕上がり比較
| 項目 | マットメディウム | グロスメディウム |
|---|---|---|
| 表面感 | ツヤ消し(マット) | 光沢あり(グロス) |
| 発色 | 落ち着いた色調 | 鮮やかで深みが増す |
| 透明感 | やや低下 | 高まる |
| 適した表現 | 静けさ・柔らかさ・落ち着き | 華やかさ・透明感・インパクト |
| 向いている作品 | 抽象画、和風アート、静物画 | ポップアート、風景画、光を強調する作品 |
使い分けの具体的なシーン
1. 落ち着いた雰囲気を出したい場合 → マットメディウム
- 例:モノトーンを基調とした作品
- 例:柔らかい光の中にある静物画
→ マット仕上げは余計な反射を抑え、作品に「静けさ」や「上品さ」を与えます。
2. 鮮やかさや透明感を強調したい場合 → グロスメディウム
- 例:海や空などの自然風景
- 例:ビビッドカラーを使ったポップアート
→ グロス仕上げは色彩の深みを増し、視覚的に力強い印象を残せます。
3. 部分的に使い分ける
作品全体をマットに仕上げつつ、ポイント部分にグロスを使うことで、視線を誘導する効果が得られます。
- 花の中心だけをグロスで強調する
- 背景はマットに、主題はグロスで輝かせる
制作に取り入れる実践的な方法
① 絵具に混ぜる
- メディウムを直接絵具に混ぜ、質感を変える方法
- 均一な表面感を得たい場合に有効
② 上塗りとして使う
- 完成後に表面へ塗布し、仕上げコーティングとして使用
- グロスはニスのように輝きを増し、マットは反射を抑えて落ち着いた印象に
③ レイヤーごとに質感を変える
- 背景層:マットで落ち着かせる
- 前景層:グロスでインパクトを与える
→ 立体感や奥行きを演出可能
マットとグロスを混ぜて「半ツヤ」にする方法
実は、マットメディウムとグロスメディウムをブレンドすると、**セミグロス(半ツヤ)**の仕上がりが得られます。
- 6:4(グロス:マット) → ややツヤあり
- 5:5 → 中間的で自然な質感
- 3:7(グロス:マット) → 落ち着きの中に軽いツヤ感
展示環境や作品テーマに合わせて、好みの質感を作れるのが魅力です。
よくある質問(Q&A)
Q1. ニスとどう違うの?
A. ニスは最終的な保護膜を作る役割が強いのに対し、メディウムは制作途中から質感を調整できる点が大きな違いです。
Q2. 写真にするときはどちらが良い?
A. 反射を避けたいならマットがおすすめです。SNS投稿や販売サイト用に写真を撮る際には、マット仕上げの方がきれいに映ります。
Q3. どのくらい混ぜればいいの?
A. 一般的には絵具1:メディウム1の割合から試し、必要に応じて調整します。グロスは少量でも艶が強く出るので注意が必要です。
まとめ
マットメディウムとグロスメディウムは、作品の雰囲気を大きく左右する重要な補助材です。
- マットメディウム → 静かで落ち着いた表現、柔らかな雰囲気に最適
- グロスメディウム → 鮮やかさや透明感を強調し、華やかな表現に効果的
- 部分的な使い分けやブレンド → 視線誘導や独自の質感演出が可能
制作テーマや展示環境に合わせて、これらを柔軟に使い分けることで、作品の完成度と表現力がさらに高まります。